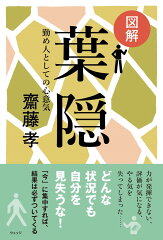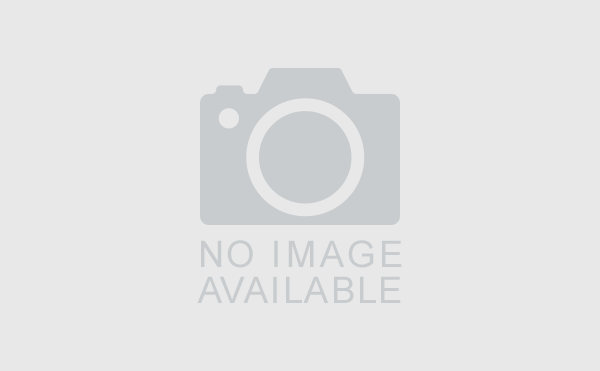齋藤孝著『図解葉隠』軽々しく現代版におきかえるのはNG!
『葉隠』は江戸時代中期に、肥前国佐賀鍋島藩士・山本常朝(現在の佐賀県)が武士の道訓や故人の遺訓などを口述したものを、佐賀藩士・田代陣基が整理・加筆してまとめた書物です。
齋藤孝著『図解葉隠』は、「葉隠」を現代版に解釈して“勤め人としての心意気”をわかりやすく説明するという意図で書かれています。
目次
山本常朝
山本常朝(つねもと)は、江戸時代の佐賀藩の武士。1659年生まれ。父が70歳のときの子どもで、11歳で父と死別。
42歳の若さで隠居、出家します。60歳没。
田代陣基
田代陣基(つらもと)も江戸時代の佐賀藩の武士。1678年生まれ。19歳より鍋島藩・藩主に祐筆役として仕えます。しかし解雇され、失意の中、同僚の先輩からの紹介で山本常朝の庵を訪れ、感銘して書を残す決意をします。71歳没。
『葉隠』
『葉隠』は、佐賀藩に仕える武士を対象に武士の心構えなどが書かれている書物なので、始めは佐賀藩の一部の武士の間で読まれていました。
明治時代に入り、『葉隠』11巻の分量を5分の1まで削った本が刊行されます。
その後、軍事時代の日本の中で、都合の良いように解釈され、評価されていきます。
人気作家だった三島由紀夫が『葉隠入門』を執筆し、賛嘆したことも世間に影響を与えたと思われます。
「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」
この一文が『葉隠』の中で最も有名な文言であり、「聞いたことがあるかも」と言う人も多いようです。
語訳
武士道とは、死ぬことをいとわないことである。
太平洋戦争中に「死をいとわない日本の武士道精神」として強要された事実もあるようです。悪い解釈ですね。
本書の解釈
齋藤先生の解釈では
「朝と夕べに思い返し、改めて死身(ししん)になる。死ぬのを恐れない体のあり方。人間は死ぬものだとわかると、思い切り好きなことをしようと思う。死身になるとき、人は自由を得ます。常に死身でいれば本気になるので、油断もなくなり、ミスは絶対的に少なくなります」
感想
自由になるかなぁ~。
「死ぬ」ことは「怖い」ことと思うのが人間の本能。「死ぬ」という恐ろしいことを思えば、「これしきのこと」「死ぬよりマシ」だから頑張ろう
と前向きに思うように。
保身について
本書の解釈
「死身」の反対は「保身」です。生きようとするのは悪いことではありませんが、生きることに執着する人は、自分の利益を一番に考えようとします。
感想
“生きようとするのは悪いことではありませんが”という一文は解せません。
“生きようとするのは”、当たり前です。
“昔はせん気の事を臆病ぐさと申し候”
腹痛で歩けなくなった人を「腰抜け」と叱られ切腹を申しつけられた。
本書
今の時代はそんなことはないから良かったなと思いましょう。
感想
ぬるい。
これは「間違いです!」
と強く否定すべきです。
切腹=自殺
してはいけないのです!
介錯
介錯とは武士が切腹をしたのち、クビを切る仕事です。介錯はやりたがらない人が多かったとか。
しかし介錯を命じられたら
「武士として本望です。命じてくださりありがとうございます」
と思うようにと。
本書
それを現代的に考えると
「イヤな仕事がまわってきても、気持ちよく引き受け、断らないことが大事です」
とのこと。
感想
イヤな仕事を断らないたとえに「介錯」を用いてはいけません。重さが違います。
「介錯」は人殺しです。
絶対にやってはいけない行ないです。
世の中には「やってはいけないこと」があるのです。
そのひとつが人殺しです。
殺し屋に殺しを依頼されたら、やりますか?
それと同じことだと思います。
「介錯」を例にとりあげるならば、
「世の中にはやってはいけないことがある。自分の意志を貫くことも大事」
という教えにしてほしいです。
『図解葉隠』
齋藤先生は、「死」に対する考えが軽いですね。
軽いからこそ、「葉隠」を現代版におきかえて本にしようと発想できたのでしょう。
武士の時代は、「死ぬ」ことに対する知識を持っている人が少なかったため、簡単に人殺し、切腹が横行していた間違った時代だったこと、そして簡単に死を選んではいけないことを強調して記してほしかったです。
「死」に対する研究不足、知識不足の人は、この分野は書かないように、触れない文言を選んで書いてほしいです。
「葉隠」を現代版におきかえる文言は慎重に選ぶべきだったでしょう。